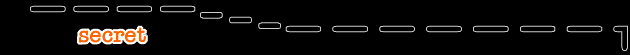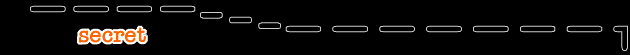|
VOLUME No.45 (2005.9.20)
|
偉大なるミュージシャンについて敬意を表し、
ピックアップしていく「ロックの巨人」。
第4回目の今回は、特定のミュージシャンというよりも、
音楽の1つのタイプである「ジャム・バンド」の魅力について語って頂きました。
|
ミュージシャンには、いつも同じ完璧な演奏をしたいと思うタイプと、
今しか出来ないものを目指しているという2通りがいると思うんだ。
ロックを演っている人達というのは、その後者の意識を持っている人達の方が強いと思うんだ。
で、今回は同じことは2度やらない(やれない?)代表選手達を語ってみます。
一般的にはそういうバンドを「ジャム・バンド」と呼ぶんだけど、
つまりジャンルとまではいかないけど、ロック・バンドにおけるタイプとか
カテゴリーの1つと知っておいてもらえればいいかな。
そんな彼等の一番の特徴は即興演奏。特にライブにおいてその特徴は顕著になる。
プレイがどんどん広がっていくから、1曲の時間が30分な〜んて事もざらにある。
当然番組の中で紹介しようにも、かけられないんだよ。
だから今回は「要の小部屋」で取り上げてみようと思ったんだ。
昔は「ジャム・バンド」なんていう呼び方はなかったと思うんだけど、
今思うとそういう音に俺が初めて出会ったのがThe Allman Brothers Bandだった。
スタジオ盤とライブ盤の違いにびっくりしたもの。
まぁ、彼等の場合は自然発生的に即興演奏で広げていく曲と、
ある程度決まった中で演奏する曲と分けていたので聴きやすさもあって
高校生の俺でも面白く聴けた。
曲もいいし、なによりもDuane AllmanとDicky Bettsの二人のギタリストの
コンビネイションに俺は胸躍らせたよ。
そしてジャム・バンドで最も知れらた存在がGrateful Dead。彼等の場合は、
今もよく聴くけどまだわからない部分が多い。アルバムごとに色が変わっていく。
「Live Dead」なんていうムチャクチャ観念的なアルバムがあるかと思えば、
これただのカントリーバンドじゃん、なんて眠くなる曲もある。
でも、このGrateful Deadはアメリカのライブバンドの代表格だったんだよ。
なんたって彼等がツアーを始めると全米中のDead Headと呼ばれるおっちゃん、
おばちゃんが仕事そっちのけで一緒にツアーを廻ってた。
特に知的層に絶大の人気を誇っていて、弁護士から学者から毎回追っかけ状態だったんだ。
73年にはThe Allman Brothers、The Bandとともにワトキンス・グレンというコンサートで
何と60万人も集めてしまった。そんな日本では超マイナーなアメリカの国民的バンドがGrateful Deadだ。
実はアメリカにはそんなバンドも多くて、まぁ、決して音楽シーンのメインになる事はないんだけど、
そういうバンドの存在も、それを楽しむお客さんもちゃんと根付いているアメリカっていうのは、
ライブ好きの俺にとってはとってもうらやましかったりもする。
エリック・クラプトンが率いたあのCream(彼らはイギリスだけど)も即興演奏を得意としたバンドだったから、
彼らのライブにおける凄まじいインプロビゼーションにジャム・バンド的な要素を感じる事も出来るけど、
どっちかと言えばジャズ的なアプローチといえるかも知れない。
そんな60年代・70年代のバンドを受け継ぎ、90年代になるとPhishが現れた。
彼らはGreatful Deadの後継者と呼ばれていたんだ。
実際彼らが出てくるまで、ジャム・バンドというカテゴリーというか流れを、
そんなには意識してなかったんだけど、
彼らの99年の初来日を観た時に、なるほどねって気が付いた事も幾つかあったんだ。
ちょっとマニアックな説明になるけど、ミュージシャン達が演奏する時には必ずルールがある。
それは曲であってもいいし、メロディ・ラインだけでもコード進行だけでもいいんだけど。
そこからその日にしか出来ない音楽を作っていこうとするのがジャムバンド。
いくら即興とはいっても元になるものや原形が何もないと音楽にならないし、
人に聞かせるのに値しなくなっちゃう。デタラメと即興は全然違うんだよ。
例えばレコーディングという形で1回録音したものをテーマに演ったりするパターンもある。
リハーサルや遊びで創った部分もある。
そういう音をライブでどれだけ広げられるかを、自分達で楽しむわけだ。
そうして広げていく中で、フレーズも変わるだろうし、テンポやキーも変わっていくんだけど、
ミュージシャンというのは、長い事やっていく内に、変化する時の匂いを
自分達の中に持つんだよね。あれが来たらこうだ…とかね。
例えば、ドラムで言えば、4小節の最後に、ダカダカダカてな感じでフィルインが入るでしょ。
あれをどうしてやるかというと、そこを1つの区切りにしているんだよ。
つまり、これが来たらこの次は変えてもいいよとか、
変わるよってなスタンスを皆んなに与えてる(示す)わけだ。
専門的になっちゃうけど、例えば、ある一定のパターンで曲が進んでいるとするでしょ。
そんな中、いきなり別のパターンや展開に持っていくのは無理があるでしょ。
だからそういうフィルインを入れる事によって、つなぎをスムーズに持っていけるんだ。
少しでも分かって欲しくてドラムで説明したけど、もちろん他の楽器にもそんな状態がある。
そうやって1曲ができ、ジャム・バンドっていうのは全体的にそういう雰囲気が流れているとも言える。
それからね、この辺はGrateful Deadから受け継がれた部分だと思うんだけど、
Phishは他のアーティストのカバーもたくさんやるんだよね。
でもこのPhishの恐ろしい所は一曲やるんじゃなくて、アルバムそのままやっちゃう。すっごいだろ。
本家もやったことないような、例えばThe Beatlesの「White Album」全曲とか、
Pink Floydの「Dark Side Of The Moon」、
挙げ句の果てにはThe Whoの「四重人格」まで全曲フルカバー。ありえない。
そんな歴史的名盤を彼らなりに再構築して、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で、
どうにか表現しようと一生懸命聴かせてくれる。もちろん笑いの部分もあるんだけど、感動もんですよ。
彼らは優れたプレイヤーであると同時に素晴らしき音楽ファンでもあるんだよね。
かと思えば99年のフジ・ロック・フェスティバルの初来日、俺は2日目しか見てないけど、
3日間同じ曲が1曲もなかったんだってさ。
彼らはその日に作ったメニューでやっていくらしいんだけど、
そういう何かを始めようとした時に、メンバー皆んながそれに合わせられる、
のっていける技量もちゃんと持っているのもジャム・バンドたる所以でしょ。
そんな中で最近の俺のお気に入りはRobert Randolphっていうスティール・ギター・プレイヤーのバンド。
やっぱりスタジオ盤よりライブ盤のほうが圧倒的にいい。
ある意味、型にはまらないっていうのかな、やっぱりジャム・バンド独特の雰囲気を持っている。
基本的にはRobert Randolphの自由奔放なギターが中心なんだけど、
曲もどんどん展開していくし、自分がギターを弾かない時は、前に出ていって踊ってる。
そういうアーティストにとってCDは単にテキストでしかないのかも知れない。
もちろんCDを軽んじているわけじゃないよ。
ライブを基本に考えてるようなバンド、ライブでどれだけのものが表現出来るか…を
考えているようなバンドにとっては、基本形のCDがあって、そこからその日のコンディションや
お客さんの雰囲気でどれだけスケールアップできるかがその存在理由となるんじゃないかな。
こう語ってくると、ジャム・バンドって自分たちの自己満足で演奏してるみたいでけど、
じゃお客さんは何を楽しみにするかっていうと、その日に生まれてくるふたつと同じものがない音楽だよね。
なんてこというと、即興性を理解できるレベルの高さみたいなものがないと
楽しめないんじゃないかと思っちゃうかもしれない。
確かに音楽への好奇心は高い方がいいのかもしれないけど、
でも演る側は、別にそんな高尚な事をお客さんに求めているんじゃない。
最終的に何かを感じてくれれば、それでいいんだよ。
ジャム・バンドの演奏は基本的には長い曲が多い。平気で1曲30分とかあるから。
でも演る側にとって30分間ズ〜っと高密度なんて事はないわけ。
展開していく中で、ある部分ではリズムだけにしたりして、いい意味での適当な、
まぁ力を抜いたパートもあるわけ。
自分たちでも次の展開がどうなるのかわからないんだから、単純に受け止めて楽しめばいいんだ。
Phishのライブには毎回野外で何万人もの人が観にくるんだけど、
その中には踊っている人もいるし、観て、聴いている人もいるし、
大体さ何万もの人が集まったら、後ろの方の人なんてほとんど見えないんだろうから、
その雰囲気を自分なりに楽しんでる。それでいいんだよね。
まあ、好き嫌いはわかれるところだろうけど、こうやって音楽を聴く以上に
(もちろん聴いてるだけでも十分すごいけど)感じるってもなかなか面白いもんだと思うよ。
最近では、共にAllman一派だけどGov't Mule やThe Derek Trucks Band も気に入ってよく聴いてるんだ。
そういえば去年、アメリカのクリーブランドにある
「The Rock and Roll Hall of Fame and Museum(ロックの殿堂博物館)」に行ったんだけどさ、
館内に入ったすぐの所に、Phishが野外のコンサートで使った巨大なホットドックが吊るされていたんだ。
彼らは、この大きなホットドックに乗って登場したんだって。
なんでそんなことしたかっていうと、ライブで後ろの方、
つまりステージからは遠くの方にいるお客さんは、
前の方のお客さんと同じ気持ちでいるのか?てな事を考えて、
ある時、そのホットドックに乗って、後ろから出てきて、
後ろのお客さんを中心に演奏したかったんだってさ。
やっぱこいつら、すごいよ。
ジャム・バンドって言い換えれば究極のライブ・バンドって事になるんじゃないかな。
一応俺達もライブバンドって呼ばれているけど、ライブ・バンドの魅力はって問われれば、
結局いつものセリフになっちゃうけど、やっぱり観た人にしか分からないよなぁ。
|
|
| 要の小部屋BACKNUMBERへ |
Copyright(C)2001 JAPAN FM NETWORK All rights reserved.
|