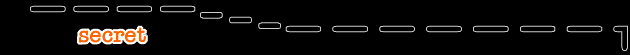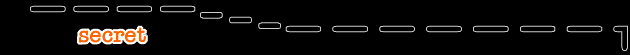偉大なるミュージシャンについて敬意を表し、ピックアップしていく「ロックの巨人」。
第3回目の今回は、レッド・ツェッペリンについて語って頂きました
|
レッド・ツェッペリンといえば、偉大なるロックの王として、神格化されていながら、その一方で本質は何も語られていないような気がするんだ。
確かに彼らのサウンドで耳に残るのは、ヘビィなギターのリフだったり、その正反対にいるようなブリティッシュ・フォークの匂い、それをロックの象徴ともいえるギターで表現したジミー・ペイジの才能。
ロバート・プラントの絞り出すようなハイトーン・ボーカル。何が飛び出すかわからないライブ。
いろんな人がZEPを語るけど、何故こんなマニアックなバンドが世界を制したのか俺なり分析したいと思ったんだ。
同じ時代に活動してたFreeなんかにもかっこいいリフはいっぱいあったし、ポール・ロジャースという素晴らしいヴォーカリストもいた。
あるいはクラプトンがいたCreamだって、歌も含めた曲の質の高さ、そして彼らの特徴でもある演奏のインプロビゼーション(即興演奏)も、これまた新しい時代の幕開けだった。
ところがZEPのヴォーカリストのロバート・プラントは素晴らしいシャウトやらハイトーンのみならず、2度と同じ歌を唄わないっていうのか、唄でとことんインプロビゼーションしちゃうんだよ。
そんなの聴いた事がないでしょ。確かにブルース・ロックとか一般的なロックの曲って、メロディよりリフで覚えてたりはすることは多いけど、プラントの歌は歌であって歌でない。
語り、あるいは叫びと言っていいかもしれない。おそらく、ペイジがありそうでなかった不思議なギターのリフを創って、それに言葉をのっけていくっていうのかな。
Creamの場合、ライブで演奏がどんどん違った方向に進んでいく、つまりこれがインプロビゼーションだけど、あっこっちに行っちゃうのはあくまで楽器のプレイであって、
唄メロ自体はスタジオ盤とは、そんなには変わらない。それはそうだよ。歌をもって或いはメロディ・ラインをもって、曲と大抵は認識するんだから。
でもZEPは、唄までどんどん広がっていっちゃう。インプロビゼーションというのは、あくまでも曲の拡大解釈であって、基には曲の構成やらメロディが存在するわけ。
それすらも広げていったしまったレッド・ツェッペリン。
聴く人によっては同じ曲に聞こえない場合があるだろう。ちょっと専門的は話になるけど、Creamやちょっと後に出てくるHumble Pieとかは、1コードの中で広げていくって事はあまりしなかった。
やっぱり根がブルーズだから、さっき言ったように、あくまでも曲の、つまり「音楽」という範疇で、プレイしてた気がする。
これに対してZEPはそういうのを超越しちゃってた位置に立ってたような気がするんだ。
同じような事を延々と繰り返しながら、曲自体がどんどん広がっていっちゃうわけ。ヘタすりゃただのデタラメだよ。そんな事やっていたのって、それまでなかったからね。
逆に言えばZEP以外が演るとかっこ悪いっていうか、もたないとかあるんだよ。う〜ん分かりにくいかな?
付け加えて言えば、延々と繰り返すとは言いつつもどこかで曲を終わらせなければならないよね。
ある程度、決められた範疇の中で自由に演奏していれば、ここで終わる、あるいはここで元に戻るっていう決め事があるんだけど、それを決め事と感じさせないっていうのかな、
どこまでも登っていくようでいて、きちんとキメる部分が存在する。それはメンバーの中に暗黙のルールや、インプロビゼーションとは言いつつも、同じ空気を感じられるからできるわけ。
そしてそれこそがライブ・バンドなんだよね。これはアメリカのジャム・バンドといわれる、例えばAllman BrothersやGrateful Deadにも通じるものだけど。
もう少し乱暴な言い方で説明すると、例えばスタジオ盤というきっちり作られた基本があるでしょ。「スタジオ盤」を「家」に置き換えて、説明すると、Creamのライブは、内装を変える感じだよね。
つまり「家」というベーシックな部分はそのまままで、それに合わせて中身(内装)を変える。
一方、ZEPのライブは「家」そのものを建て替えてしまうわけだ。
この2つのバンドがやろうとしていた事は、いわばブルーズの発展型だよね。でもその方向というのはお互い全く逆に向かっていると思うんだ。
ブルーズをよりジャズ的なアプローチで作っていたのが、Creamだし、ブルーズを拡大解釈して新しいジャンルと創ろうとしていたのがZEPのような気がする。
俺は当時(1968年〜69年頃)小学生から中学生になろうとしていた時期だったけど、1番聴いていたのが、この2つのバンドでね。聴かない日はなかった。
クリームは「Wheels of fire」、ZEPは1枚目と2枚目かな。まぁ聴いていたというよりも、一緒にギターを弾いてたといった方が正しいかも。
ある意味、教科書みたいなものだった。当時それらはニュー・ロックと呼ばれていたことからも、他といかに違うモノだったがわかるだろう。
もちろん違ったアプローチでかっこよかったバンドも沢山いたのも確かで、Frank ZappaやPink Floydもすでに名声を得ていた。
しかし2005年の今でもツェッペリンは凄い、凄いと皆が言うのは何故なんだろう。
もちろん俺自身が音楽リスナーとして聴いても、ミュージシャンという立場で聴いても、彼らが凄いのは間違いないし、蘇る映像にその唯一無比のパワーを感じることもできる。
今でも彼らの1枚目から4枚目まではよく聴いてる。例えば、年を重ねるごとに段々と理解できていく音楽ってあるでしょ。The Bandなんかまさにそうなんだけどさ。
でもツェッペリンは聴く度に新しい発見があるとか、年を取って分かるとかそういうものじゃなくて、あの時代の、あのメンバーだから出来た刹那的な音に惹かれているんだと思うよ。
ZEPの本質を理解しようという事は、聴く側の力量がすごく要求される気がするんだ。分かりやすいバンドか、そうでないバンドかと問われたら、奥深いし、分かりにくいバンドなのかもしれない。
これはあくまで俺の考えだけど。でも分かりづらいにも関わらず、俺の気持ちを捕らえて離さないのは、それは哲学みたいなものだからかもしれない。
だから本当に理解しようと思わないと、なかなか本質まで辿り着けないような気もするしね。もちろん純粋に音楽として楽しんでいればいい。
だけど俺にとってのZEPの凄さというのは、ついつい哲学みたいな領域までいってしまうんだ。
たった2度の来日公演、それを2回ともたまたま見られた俺は、今でも本当にこのバンドに出会えて、というか見られてよかったなって思う。
もし俺が彼らの音楽を当時、聴くだけに終わっていたら、こんな風に彼らに哲学を感じることはなかったろう。 |
|